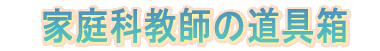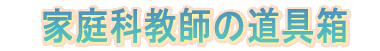| 指導項目・指導事項 |
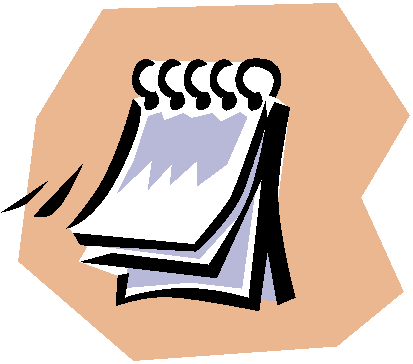 テキストコンテンツ テキストコンテンツ
 動画コンテンツ 動画コンテンツ
 静止画コンテンツ 静止画コンテンツ
 クイズ形式 クイズ形式
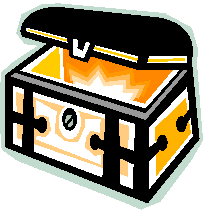 指導案&教具・教材等セット 指導案&教具・教材等セット |
備考・概要 |
| A 生活の自立と衣食住 |
|
|
| (1)中学生の栄養と食事 |
|
|
ア 食品の役割,健康と食事との関わり
|
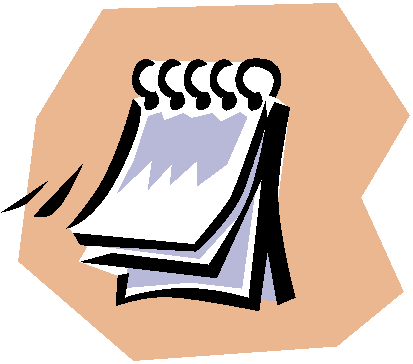  朝ごはんの効用 朝ごはんの効用
|
集中力アップと肥満予防の観点から,朝ごはんの必要性を説明してあります。(女子栄養大学副学長 香川康雄先生) |

小腸,小腸壁,柔毛の構造
|
理科で「消化・吸収」を学ぶ前に家庭科で授業をする際,内臓で吸収される画像イメージが欲しいというリクエストにお応えして,探してきました。時間は約30秒。食物=栄養素ではない(例;「肉」≠「たんぱく質」)こと,栄養素は,こんなに小さな小腸の柔毛から吸収されるのだから,とても小さく分解されるのだよ・・・ということをイメージ的に捉えさせるのに使えると思います。 |
イ 栄養素の種類と働き,中学生の栄養の特徴
|

栄養素の問題(3択クイズ)
|
「Hi! 家庭科」内の教材バンクコンテンツ。「栄養の基礎知識」が上位コンテンツです。全10問,採点機能付き。栄養素について簡単に学んだあとの確認に有効。 |
ウ 食品の栄養的特質,栄養を満たす1日分の献立
|

えいようそクイズ1(3択)
|
「Hi! 家庭科」内の教材バンクコンテンツ。「栄養の基礎知識」が上位コンテンツです。全10問,採点機能付き。栄養素のことと,どの食品にどんな栄養素が含まれているか学んだあとの確認に有効 |

えいようそクイズ2(複数回答)
|
「Hi! 家庭科」内の教材バンクコンテンツ。「栄養の基礎知識」が上位コンテンツです。全5問,採点機能付き。どの食品にどんな栄養素が含まれているか学んだあとの確認に有効で,上記の「3択式」よりほんのちょっとレベルアップ。 |

六つの基礎食品群の問題(○×クイズ)
|
「Hi! 家庭科」内の教材バンクコンテンツ。「栄養の基礎知識」が上位コンテンツです。全12問,1問ずつ正解と解説を確認しながら進みます。食品群と栄養素の関係を学んだあとの確認に有効。摂取量についての解説がありますが,基準が高校生女子になっているので,この点のみ配慮が必要です。 |

六つの基礎食品群クイズ(3択式)
|
「Hi! 家庭科」内の教材バンクコンテンツ。「栄養の基礎知識」が上位コンテンツです。全12問,問7から先が摂取量に関する問題で,基準が高校生女子になっていますが,問11の「5群」について注意しさえすれば,あとは中学生の基準とほとんど同じなので大丈夫です。食品群別摂取量のめやすを学んだあとに有効で,上記の「六つの基礎食品群の問題(○×クイズ)」をやったあとにすると効果的。 |

食生活と栄養素クイズ(記述式)
|
「Hi! 家庭科」内の教材バンクコンテンツ。「栄養の基礎知識」が上位コンテンツです。ひととおり栄養素関係について学んだあとの確認に有効。問6の「単糖類」と,問8の「必須アミノ酸」のみ補足が必要ですが,理科との関連で「ブドウ糖」という言葉を出すことで説明可能。必須アミノ酸については,テレビ等で知っている生徒が多いので,難しくはないようです。 |

食品を「六つの基礎食品群」に分類しよう
|
「Hi! 家庭科」内の教材バンクコンテンツ。食品の写真を,6つの食品群枠にドロップすることで確認していきます。どの食品がどの食品群にはいるか,短時間で確認できます。 |
| (2)食品の選択と日常食の調理の基礎 |
|
|
ア 食品の品質と適切な選択
|
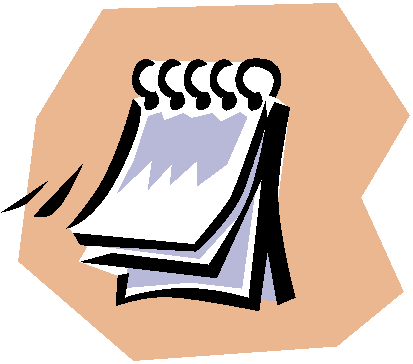
旬のカレンダー(魚)
|
魚の旬を一覧表にしてあります。印刷も簡単なので,配付資料にも便利。それぞれの魚の名前をクリックすると,「目からウロコのうんちく」を読むことができます。
味の素のサイト内。味の素のコンテンツは,レシピ集やアミノ酸についてのことなど,充実しています。 |
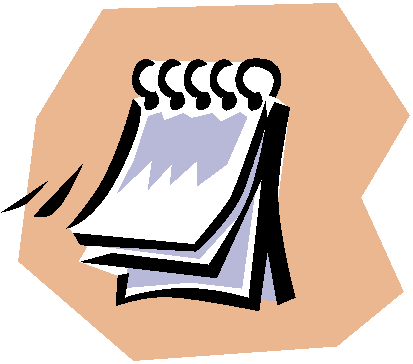
旬のカレンダー(野菜)
|
野菜の旬を一覧表にしてあります。印刷も簡単なので,配付資料にも便利。それぞれの野菜の名前をクリックすると,「目からウロコのうんちく」を読むことができます。
味の素のサイト内。味の素のコンテンツは,レシピ集やアミノ酸についてのことなど,充実しています。 |
イ 簡単な日常食の調理
|
|
|
ウ 食生活の安全と衛生
|
|
|
| (3)衣服の選択と手入れ |
|
|
ア 衣服と社会生活とのかかわり,着用の工夫
|
|
|
イ 衣服の計画的な活用と適切な選択
|
|
|
ウ 衣服材料に応じた手入れと補修
|
|
|
| (4)室内環境の整備と住まい方 |
|
|
ア 家族が住まう空間としての住居の機能
|
|
|
| イ 安全で快適な室内環境の整え方と住まい方の工夫 |
|
|
| (5)食生活の課題と調理の応用 |
|
|
ア 日常食や地域の食材を生かした調理の工夫
|
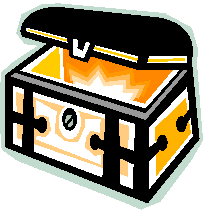
H17年熊本県大会指導案セット |
必修A-(1)-アと関連させて取り扱うことができます。「地産地消」のよさに注目させ,今後食品を選択するときの視点を学ぶことができます。 |
イ 会食の計画と実践
|
|
|
| (6)簡単な衣服の制作 |
|
|
ア 衣服の基本的な構成
|
|
|
イ 簡単な衣服の製作の計画と実践
|
|
|
| B 家族と家庭生活 |
|
|
| (1)自分の成長と家族や家庭生活とのかかわり |
|
|
| (2)幼児の発達と家族 |
|
|
ア 幼児の遊びの意義と重要性
|
|
|
幼児の観察や遊び道具の製作
|
|
|
イ 幼児の心身の発達の特徴
|
|
|
幼児の発達とかかわる家族の役割
|
|
|
| (3)家庭と家族関係 |
|
|
ア 家族や家庭の基本的な機能
|
|
|
家族の生活と家族関係
|
|
|
イ 家庭生活と地域の人々とのかかわり
|
|
|
| (4)家庭生活と消費 |
|
|
ア 物資・サービスの選択と購入及び活用
|
|
|
販売方法の特徴と消費者保護
|
|
|
イ 環境に配慮した消費生活の工夫
|
|
|
| (5)幼児の生活と幼児との触れ合い |
|
|
ア 幼児の生活に役立つものづくり
|
|
|
イ 幼児との触れ合いやかかわり方の工夫
|
|
|